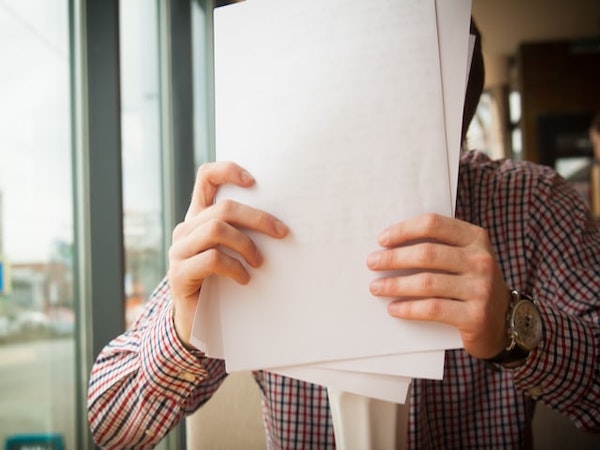教員の自己評価シートをどうやって書いたらいいか分からないという方は多くいると思います。正式な書類ではありますが、書き方に迷ってしまう部分でもありますね。
- 自己評価シートの書き方を詳しく知りたい。
- 元教員の立場から、いい書き方を教えて欲しい。
上記のように考える人に向けて、実際の体験談から記事を書いていきたいと思います。
3分程度で簡単に読むことができますので、ぜひ見てみてください。
教員の自己評価シートの例文について

自己評価シートの書き方についてですが、型を覚えてしまえば割と簡単に書くことができるかと思います。書くべき項目は以下の4つですね。
- 目標
- よくできた点
- 改善点
- 解決策
順番に解説していきたいと思います。
目標
おそらく、学期はじめなどに書くことになるのがこの「目標」になるかと思います。目標についても、何を書いていいのか迷ってしまいがちですよね。
とはいえ、それほど悩んで書く必要はありません。自分ができそうな範囲のもので書くのがいいです。
学期はじめの目標については、「ざっくり」と書くのがおすすめです。具体的な目標を書いてしまうと、学期の終わりに振り返った時に「何もできていない・・・」となってしまいますね。
そうならないためにも、クラスの状態を見つつアバウトな感じで書くように心がけましょう。
「子供が楽しく学習できるようにする。」「保護者と良い関係を築けるようにする。」などが結構いいかと思います。
振り返り
目標に対して、学期の終わりで書くのが振り返りになります。振り返りについては
- よくできた点
- 改善点
- 解決策
の順番で書くと、結構うまくいきます。
よくできた点だけを書くのは教員の世界ではありがちですが、謙虚さに欠けたり若い先生だと生意気に取られてしまうことがあります。周囲からの嫉妬の対象になったりもしますね。
また、改善点だけを書くのもNGです。謙虚で素敵ではありますが、教員の世界では謙虚さがネガティブに捉えられることが多いです。
なので良くできた点と、改善点をバランスよく書くように心がけていきましょう。
また改善点を書いた後は、かならず解決策を書くようにしましょう。ただ改善をするだけでは具体性がないので、管理職も心配になったりします。
管理職が不安になると、教室に来る回数なども増えてくるので授業がしにくくなることでしょう。
そうならないためにも、自分でしっかりと解決策を考えて書いておくことがとても大切です。
具体的な例文

では、実際にどんな風に書いていけばいいのでしょうか。具体的な例文を①〜④で挙げてみました。
①目標→ITを活用しつつ、子どもが楽しく取り組めるようにする。
①振り返り→授業の中でタブレットをテレビなどに接続しながら子供が興味をもって取り組めるようにした。反応として、今まで授業に興味がなかった3人の児童が授業に興味をもつようになった。今後は、さらに多くの児童が興味を持つように、主要科目でも導入を考える。
②目標→ITを活用しつつ、子供が楽しく取り組めるようにする。
②振り返り→授業の中で、タブレットをテレビに使うことで子供が見られるようにした。反応として、今まで見なかった3人程度の子が興味を持つようになった。今後はさらに〜する。
③目標→保護者と良い関係を築けるようにする。
③振り返り→週に1回程度、学級通信を発行してきた。保護者からはクラスの様子がわかるようになってよかったなどと評判が良かった。とはいえ、授業の内容などは詳しくわからないという声があったので、今後は載せていくようにする。
④目標→いじめや悩みなどがわかるように、「生活ノート」を実施する。
④振り返り→生活ノートを作ることで、子供の様子を深く知ることができた。特に3名の児童からは悩みを聞くことができて、未然にいじめを防ぐことができたと思う。とはいえ、まだ悩みを言えていない児童もいると思うので、学校でのコミュニケーションなども増やす。
完璧でなくてもOK

自己評価シートについては、完璧でなくてもOKです。よほどテキトーでなければ、おそらく管理職は細かい点まで見ていないと考えていいでしょう。
また、自己評価シートを書いた後には面談を行っている学校もあります。自己評価シートの内容についても、面談で詳しく聞くことができますので評価シートはそれほど力を入れなくてもOKですね。
面談で詳しく話せば特に問題ないかと思います。
また、組合などに入っている人は教職員全体で書き方を統一していたり記入例をもらえるケースもあるかと思います。
その場合は、学校のやり方に合わせるのがベストだと思いますね。
まとめ
自己評価シートは書くのが面倒に感じるかもしれませんが、パターンを覚えてしまえば割と楽だったりするかと思います。
今回の記事を参考にしつつ、ぜひ取り組んでみてくださいね。