「教員になったものの、ミスばかりで落ち込む」という方は多いと思います。
毎日気持ちが沈んで、辛いときもありますよね。
しかし、教員の大きなミスはほとんどないと思っています。
むしろ、多くの教員は細かいミスにこだわりすぎです。
ミスを気にしすぎることが、「長時間労働」「生産性の低下」といった問題につながっていると思います。
- どんな点に気をつけて仕事をすればいい?
- ミスしても気にしない方法を知りたい
もっと気楽に働けるよう、元教員の目線から解説していきたいと思います。
3分程度で読めるので、見てみてください。
教員の大きなミスとは?
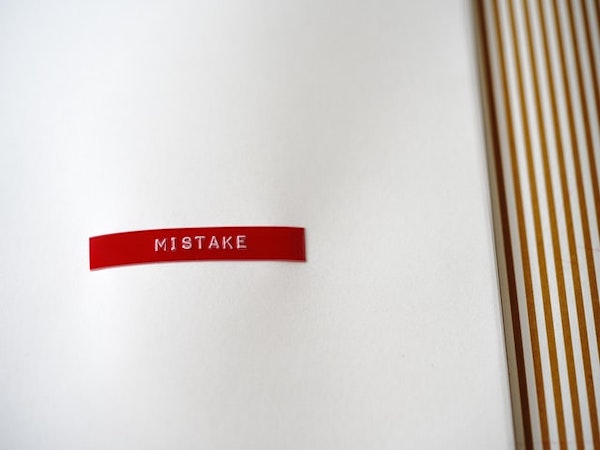
教員の大きなミスについてですが、基本的には次の2つだといえます。
・子どもの命に関わること
・不祥事(犯罪・ハラスメントなど)
教員を数年経験しましたが、この2つに気をつけていれば特に大きな問題はなかったです。
詳しく解説をしていきたいと思います。
子どもの命に関わること
子どもの命に関わることについては、気を配るようにしましょう。
とても重要なことです。
「休み時間の過ごし方などは安全か・体育の授業でケガをしないか」といった環境に気をつけることは重要です。
ケガをしたときも、足のスリ傷などはそれほど大きな問題にならないかもしれません。
しかし、首から上のケガ(頭の打撲など)は命に関わる危険があります。
すぐに保健室に行かせたり保護者に連絡をするなどの対応が必要です。
他にも、「いじめ」を担任に相談してくる子もいます。
「いじめ」も最悪の場合自傷行為に走ったり、自殺をしてしまうケースもあるかもしれません。
寄り添って、話を聞くのが大切ですね。
不祥事(犯罪・ハラスメント)など
不祥事についても気をつけるようにしましょう。
普通に仕事をしていれば、特に問題はないかと思います。
ありがちなのが、生徒に対する体罰です。
カッとなったときも、冷静に自分の気持ちをコントロールできるようにしたいですね。
また、校外でも教員という職業上気をつけた方が良いことはあります。
自転車で通勤している方などは「傘さし運転・二人乗り」などには十分に注意するようにしましょう。
教員は細かいミスを指摘しがち

「たくさんミスを指摘してもらって、細かい点まで気を配った方がいいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし教員の中には、とても細かいミスを指摘してきたり業務と関係ないことを「ミス」とする人もいます。
たしかにミスが少ないに越したことはありません。
とはいえ、気にしすぎても生産性が下がったり萎縮して仕事がしにくかったりします。
教員として働く人の中にも、「細かいミスばかり指摘されて、メンタルが参っている・・・」という人もいるのではないでしょうか?
僕は細かいミスを指摘しすぎる雰囲気が、教員で働く中で大きなプレッシャーとなっている気がします。
精神的に病んでしまう先生も多いですよね。
もちろん、ミスをなくすのは大切です。
しかし、ある程度許せるミスには目を瞑ってどんどん作業を進めていくことも大切だと思います。
あまり重要ではないもの

「ミス」といわれるものの、重要ではないものにはどんなものがあるのでしょうか?
以下にいくつか挙げてみたので、参考にしてみてください。
書類の不備・誤り
1つ目は、「書類の不備・誤り」ですね。
職員室に「紙の書類」が多いのもどうかと思いますが、その書類の誤字脱字を直すのに何往復もやりとりをすることがあります。
教員は「子供・生徒」に向き合う時間が大切なので、書類と向き合いすぎるのはどうかと思います。
ある程度、書いてあることの意味が伝わればOKでしょう。
私の場合1校目では書類で注意されることがありましたが、2校目では書類で注意されることはほぼありませんでした。
その程度のものだということです。
書類を注意されてもほぼ意味がないので、流してOKでしょう。
子どもの立ち歩き
子供が立ち歩いていると「学級崩壊だ!」みたいな感じで怒り出す先生はいませんか?
そういう教員は、授業について何も勉強していないなと感じます。
筆者は休日なども、私立の学校の勉強会に出ていました。
そこで分かるのが、優秀な先生ほど子どもを動かすということです。
動くことによってコミュニケーションが生まれますし、活動も活発になります。
子どもが立ち歩くのを怖がる先生は、シンプルに実力がないのでしょう。
立ち歩くことによって、子どもが暴れ出すのが怖いのです。
もちろん、子どもが授業を受けていないで立ち歩く場合は注意する必要があります。
しかし、マジメに授業を受けている生徒が立ち歩くのは悪いことではないです。
授業力
授業力は大切ですよね。
良い授業をして、子どもの学力を上げることはとても重要なことだと思います。
しかし、授業よりも先生の身体の方がもっと大切です。
先生が毎日元気でいてくれるのが、子どもにとって1番プラスになると思います。
「授業力をつけろ!」と怒られたからといって、休日や夜遅くまで身を削って授業準備をする先生がいます。
そのマジメな姿勢は素敵ですが、体調を崩して授業ができなくなってはもったいないですよね。
基本的に授業は毎日あるものなので、少しずつ無理のない範囲で改善しておけばOKでしょう。
言い方は悪いですが、授業がヘタなのに何年も働き続けている先生もいるので大丈夫です。
無理せずできる範囲でやっていきましょう。授業力は大きなミスではありません。
学級崩壊
学級崩壊、キツいですよね。
学級崩壊がきっかけで、体調を崩して来られなくなってしまう先生もいます。
でも、学級崩壊はそれほど大きなミスではないと思います。
理由としては、次2つが挙げられます。
- 誰でも起こす可能性がある
- 子どもに害はない
誰でも起こす可能性がある
学級崩壊というと、力不足の先生だけが起こすようなイメージがあるかもしれません。
しかし、そんなことはありません。ベテラン教員だって苦労することがあります。
なぜ、誰でも学級崩壊を起こす可能性があるのか。
それは、子ども同士のことなので何が起こるかわからないからです。
クラス替えによって友達関係が変わり、優等生が悪いことを始めるかもしれません。
良い子であっても、家庭環境によって突然イタズラをすることもあります。
いろいろな状況・人間関係が合わさって1つのクラスになります。
学級崩壊になったとしても、担任1人の責任ではないのです。
子どもに害はない
また、学級崩壊は「子どもに害はない」と考えられます。
もちろん荒れているので危険ではありますが、授業の時には監督の先生がいるはずです。
学校にいる限りは大人の目があります。
勉強についても、学級崩壊では良い指導はできないかもしれません。
しかし、優秀な子は教師の指導なしでも自分で学習をしていきます。
とにかく、学校は学級崩壊を「大きなミス」としすぎです。
多くの教員が学級崩壊に怯えていて、ダメージを受けています。
心の中では深刻にならず、気楽に考えていきましょう。
学校の方針に合わせるとラク

前項で「あまり重要ではないミス」について挙げました。
とはいえ、「重要なミスではないといっても、自分の学校では重要とされているよ!」といったケースもあると思います。
学校によって、方針がさまざまなので重要なケースも違うでしょう。
私の場合、1校目は「書類の不備」が大きなミスとされていました。
しかし、2校目ではそれほど重要視されていませんでした。(子どもの不登校などの方が大事だった)
この場合、1校目に勤務している時は「書類の不備」がないように全力を注げばいいと思います。
極端な話、他の仕事についてはある程度手を抜いても良いでしょう。学校の方針なので仕方ないです。
こだわりを持たずに、学校の方針に合わせてやっていけば割とラクかと思います。
自分の健康のためにも、学校の方針と違うものは手を抜いていきましょう。
まとめ
教員になると、ミスを指摘されることもあるかと思います。
しかし、大きなミスはそんなにありません。
自分を責めずに、気楽に教員生活を過ごしてみてくださいね。


