発達障害の子が、どんな風にコミュニケーションをとるのかは気になる部分だと思います。
コミュニケーションは人との関わりで欠かせなかったりするので、確認しておきたいところですね。
- 発達障害の子はどんな風にコミュニケーションを取るの?
- 専門家の目線で知りたい
上記のように考える人に向けて、元支援級担任の立場から記事を書いていきたいと思います。
3分程度で簡単に読むことができますので、ぜひ見てみてください。
発達障害の子のコミュニケーションの特徴について

どんな障がいを持つかによって、コミュニケーションの方法は変わってきますね。
もちろん、障がいの程度や個人によって異なる部分もありますが、解説をしていきます。
自閉症
まずは、自閉症のお子さんですね。
自閉症の場合、自分の世界をもっていることが多いのが特徴です。
友達とも関わろうとしますが、相手のことを考えるというよりは「自分が欲しい回答を相手がしてくれるかどうか」などがコミュニケーションの根っこだったりします。
学校だと、朝来てからのルーティーンなどが決まっていることが多く自分から友達に話しかけたりすることは少ないです。
ただ、自分に優しくしてくれたり興味が持てる遊びをしてくれる友達の名前は覚えていたりすることも多いです。
好き嫌いが割と激しいので、自分が嫌なことだと友達に合わせていくことは難しいことかもしれません。
人にもよりますが、とにかく自分の興味のあることを中心に取り組みやすかったりするのが自閉症のお子さんの特徴だったりします。
ADHD
発達障がいのお子さんの中でも、特にコミュニケーションが取りやすいと感じるのがADHDのお子さんだったりします。
健常児とはほとんど変わらないようなコミュニケーションができたりします。自分の気持ちなども表現しますし、割と他の子に合わせたりもするので苦労は少ないでしょう。
ただ、いろいろなところに注意が向くという特徴があるので常に焦っている感じがします。「早くして!」とせかしたり常に目が泳いでいるようなケースもあります。
そのような落ち着かない場所だと、悪気がなくても友達を叩いてしまったりトラブルが起きてしまうことがあると思います。
また、パニックになってしまうと突然暴れてしまうことなどもあります。
なのでまずは環境を整備することが大切ですね。
目に入るものを減らしたり、音の刺激などを少なくすることでADHDの子が過ごしやすくなるでしょう。
ダウン症
ダウン症のお子さんは、本当に子供によって性格が違うな〜と感じることが多いですね。
ただ、かなり愛想がいい子が多かったです。愛想がいいと友達からも好かれやすいので友達関係で悩んでいるケースはあまりみたことがないですね。
学校とかでも、割と他の子とうまくやれる傾向はあると思います。
ただ、少し頑固なところがあったりします。自分がやりたくないことなどは絶対にしなかったり、一度決めたことはなかなか曲げなかったりすることが多くあります。
ソーシャルスキルトレーニングで成長を目指す
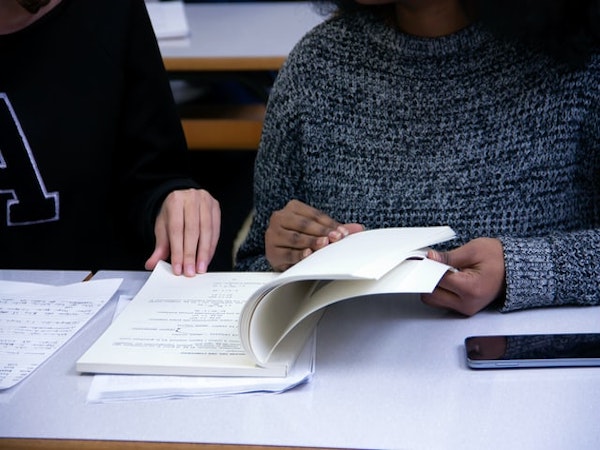
コミュニーケーションが得意か苦手かというのはそれほど問題ではないでしょう。
生まれもった障がいの程度も違うでしょうから、別に構わないです。
大切なのは、トレーニングをしてできるだけ成長していくことでしょう。今よりも少しでも成長していければ、それはすごく大事なことです。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)を通して、コミュニケーションを取る練習をしていきましょう。
学校などでも、絵カードを取り入れながら集団でやりましたが結構効果はありますよ。
絵カードだと、友達が嫌がることをしているイラストが載っていたりルールを破っている絵などがあります。
このカードを通して、やってはいけないことやコミュニケーションの取り方を学んでいきましょう。
発達障がいを持つお子さんだと、普段の生活の中でうまくいかないことが多いので自信をなくしてしまうことがよくあります。
なので、できるだけ褒めることを中心にしていくのがコツです。たくさん褒めると、子供がやる気になっているのを実感することができると思います。
親としては、できるだけ早く成長させたいと焦ってしまうかもしれませんがまずは子供のペースでじっくりと教えていくのがコツだったりします。
まとめ
発達障がいの種類によって、子供のコミュニケーションの取り方も大きく変わったりします。
SSTも活用しながら、コミュニケーションの上達を目指してみてくださいね。


