発達障害の子がパニックになったけど、対処法がわからないというケースは多くあると思います。
パニックになると、かなり焦ったりしてしまいますよね。
- 発達障害の子がパニックになったら、どうやって対処したらいい?
- 専門家の目線で対処法が知りたい。
上記のように悩む人に向けて、元支援級担任の立場から記事を書いていきたいと思います。
3分程度で簡単に読むことができますので、ぜひ見てみてください。
発達障害の子がパニックになったときの対処法

まずは、完全にパニックをなくすことは難しいことを自覚しておきましょう。
もちろんある程度の工夫で減らすことはできるものの、どうしても障がいを持つお子さんがパニックを起こすことはつきものです。
言葉で表現するのが難しかったり、健常児に合わせた環境になっているので障がいを持つ子はストレスを溜めやすかったりします。
パニックそのものをゼロにしようとすると、大人もきついと思います。
とはいえ、具体的な良い方法もありますので以下で解説していきたいと思います。
場所移動
まずは安全な場所に移動しましょう。
友達から離れた場所でもいいですし、別の部屋や教室があればそれがベストでしょう。
パニックになって友達をケガさせてしまうケースは結構多くあります。かなり危険だと言えますね。
そのため、友達から離しておくことは欠かせません。
また、感覚過敏のお子さんだと音や友達の声などがパニックの原因になってしまうこともあります。
そうならないためにも、部屋や教室を移動させたりして静かな環境を作ってあげることはかなり重要です。
受け入れる気持ち
ずっとパニックの状態になっていたり、ヒートアップしているお子さんもいます。
この場合、大人の方に障がいを持つお子さんを受け入れる気持ちがなかったりします。
「なんでそんなことをするの!」「おとなしくしなさい!」みたいな感じで相手を叱りつけたりするのです。これによって、障がい児はさらにパニックになってしまいます。
大切なのは、理由はどうであれ1度受け入れてあげる気持ちです。まずは怒ったりせず相手を受け入れてあげることから始めましょう。
「大変だったね」「わかった」などと声掛けをするとかなり効果的です。
パニックになると、親や教師が怒りたくなる気持ちはわかりますがそこはぐっと我慢です。
我慢することで、子供にも良い影響を与えます。
話を聞く
しばらくすると、パニックが収まってくると思います。しかし、収まったらそのまま放置してしまうケースもあります。もったいないです。
ちゃんと問題を解決しなければ、また同じことでパニックを起こしてしまいますね。
障がい児も、冷静になったら話がしやすくなると思うので今後のためにしっかりと話を聞いておきましょう。
「さっきはどうした?」「困ったことはある?」というように聞いていくとよいでしょう。
相手から困ったことを聞き出せれば、次に同じことでパニックになることは少なくなります。
パニックにはどんなものがある?
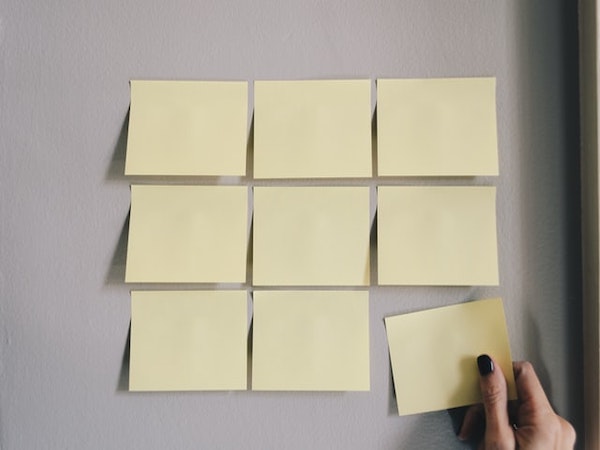
では、実際にパニックにはどんなものがあるのでしょうか。
1番多いのが、暴れてしまうことです。
怒って物を蹴ったり壊したりすることもあるでしょう。他の子を叩いたり引っ掻くケースもあります。
思いっきり泣いて、叫ぶ子もいます。
子供によっていろいろなパターンはあるものの、多くの場合暴れてしまうことが多いです。
なので前項でも挙げたように安全に配慮して、できるだけ他の子が嫌な思いをしないように気をつけていくようにしましょう。
大事なのは環境づくり

子どもがパニックを起こさないために大切なのは、環境です。
悪い指導だったりすると、子供がパニックになるたびに大人が叱りつけているケースがあります。
それを繰り返すような形です。
でも、子どもも怒りたくて怒っているわけではありません。何か原因があって怒っているわけです。
とはいえ、口でしっかりと話して伝えるのは難しかったりしますよね。
そこで必要になるのが環境を整えることです。障がいを持つ子どもが過ごしやすい環境を作ることでパニックは激減します。
毎回パニックに対処していたら大人も疲れますし、子どもも自信をなくしてくることだと思います。
お互いが過ごしやすくするためにも、環境を整えていくようにしましょう。
環境にもいろいろなものがありますが、例えば机の周りを囲って刺激をなくしたり、イスの脚にテニスボールをつけて音が鳴らないようにするなどは有名です。
できるものから試してみてください。
まとめ
子どもがパニックになった時は、大人もかなり焦る気持ちになるでしょう。
ですが、ちょっとした工夫で子供の様子も変わってくると思います。
ぜひできることから試してみてくださいね。


