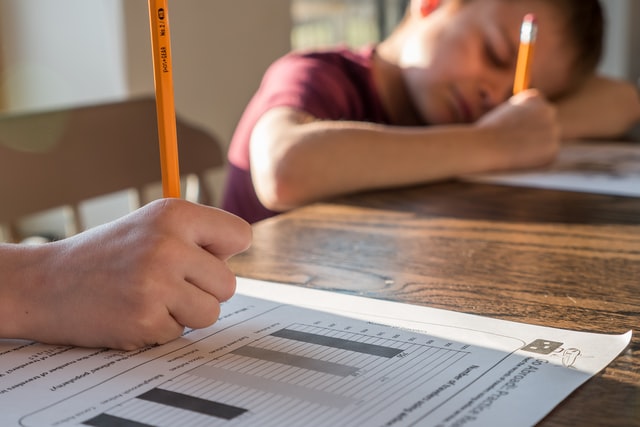宿題の量については、それぞれのクラスで大きく違っていることがたくさんあります。
子供に宿題を取り組ませていても、本当に必要なのだろうかと疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。
- 子供が宿題に取り組む意味はあるのか
- 教員をやっているけど、宿題を出す必要はあるのか。
上記のように悩む方に向けて、元教員の立場から記事を書いていきたいと思います。
宿題は必要かどうかについて
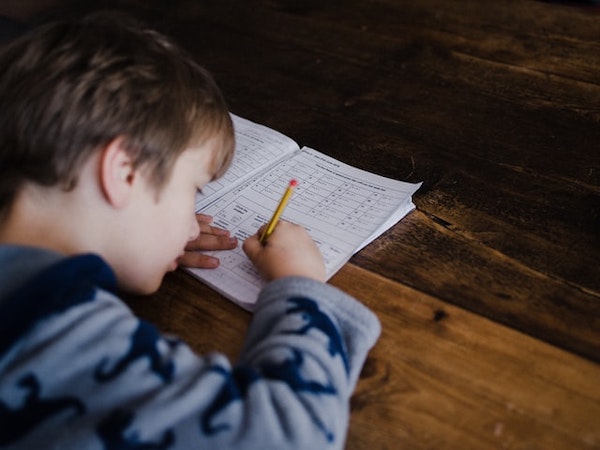
宿題についてですが、結論からいうと必要ないというのが私の考えです。
一部例外はあるものの、ほとんどのケースで宿題を出したり取り組んだりする必要はないといえます。
宿題があることによるデメリットの方が多いからです。
以下で解説をしていきます。
興味が持てないから
宿題に関しては、子どもが興味をもてないことが多いです。
勉強において、興味がもてるようにすることは大切なことです。
特にお子さんが小さければ小さいほど、興味を持てるようにするのが最優先です。
よく小学校の頃は熱心に勉強に取り組んでいて優等生だったのに、大学受験の時にはあまり成果を上げることができなかった人などを見かけませんか?
また、「読書感想文」のせいで本を読むことが嫌いになってしまった人を知りませんか?(読書感想文を否定する気はありませんが・・・。)
上記のものは多くの場合、興味がもてない学習を強制的にしてしまった結果です。
興味が持てないことに関しては、長くにわたって学習を続けることができないのです。
宿題として教員が強制的に与えるのではなくて、子供が自分で考えて必要な学習をしていく必要があります。
「学力の低い子」の親ほど宿題を欲しがる
私がクラス担任していた時は、学年の事情によって「宿題」を出していました。(本当は出したくなかったですが・・・。)
とはいえ、ほかのクラスに比べて出す宿題の量は少なかったと思います。
そうすると、きまって数人の保護者の方が「宿題を増やしてほしい!」という意見を伝えてきます。
言ってくる保護者のお子さんを見ると、きまって「学力が低い」ことがわかるんですよね。
要は、「勉強というものが他の人から強制的にやらされる嫌なこと」だということが身についているわけです。
そして、その保護者は家でもそのように指導をしている可能性が高いということです。
逆に成績の良い保護者の方は宿題などの学習面よりも「楽しく学校で過ごせているか・体調は大丈夫か」などの生活面を気にしています。
無理矢理勉強させることよりも、安定した学校生活を送れることが学習において1番大切なことを知っているからです。
学力の低い子はやってこない
宿題に関しては、全員が取り組めるようにある程度レベルを同じのものを配るようにします。
もしくは学力の低い子が取り組んだり、1人でもできるように易しめの問題になっていることが多くあります。
しかし、そもそも学力の低い子は宿題をやってこないことが多いです。クラスに1〜2人くらいは毎日のように宿題をやってこない子がいます。
なので、そもそも宿題を出す意味があまりないんですよね。
また、学力の高い子に関しても「レベルの低い宿題」に取り組ませることになってしまうので時間のムダになってしまいます。
意外と得することが少なかったりします。
主体性が身に付かない
「主体性が身に付かない」というのも、宿題の大きなデメリットです。
学習指導要領では「主体的な学び」を大切にするようにいわれていますから、主体的に学べるようにしていくことはとても重要です。
しかし、教師から強制的にやらされる「宿題」では主体的な学びをすることができないでしょう。
自分の得意科目は何なのか。どんな学習をすれば成績を伸ばすことができるのか。などを自分で考えられるようにしていくことが大切です。
社会人になってからも、他の人からの指示を待っているだけでは仕事をすることが難しいはずです。
自分で考えて、自分で行動する力を身につけるためにも宿題はなくしていく必要があるといえます。
宿題が必要なケース

とはいえ、宿題が必要なケースもあると感じています。
それは「経済的な理由」によるものです。そもそも教材がなければ勉強自体が難しいですから、宿題を出して教材を作っておく必要があります。
しかし、教材が買えないほどの貧困はかなり少ないと考えて良いでしょう。学習した教科書やノートを見直すだけでも十分に勉強になります。
また、最近ではネット環境を使ってYouTubeなどで楽しく学習することもできます。
なので、教師が無理に宿題を出す必要はなくなっているといえるでしょう。
まとめ
この記事では、宿題は不要であると書きました。
とはいえ「宿題」については、答えのないテーマだと感じています。
記事を参考に、学習に役立てていただければ幸いです。