支援学級に偏見はあるのだろうか?と不安に思っている方は多くいると思います。
お子さんが安心して通うためにも「偏見」については、確認しておきたいところでしょう。
- 支援級には、偏見がないだろうか
- 現場目線の様子が知りたい。
上記のように悩んでいる人に向けて、元教員の立場から記事を書いていきたいと思います。
3分程度で簡単に読むことができますので、ぜひ見てみてください。
支援学級の偏見はあるのか

支援級の偏見についてですが、「多かれ少なかれ、ある」というのが結論です。
やはり支援級にいると、普通級の子とは違って見られることは避けられないと思います。
授業の受け方や学校生活の仕方などが普通級の子とは違ってくるわけなので、偏見は避けられないことでしょう。
とはいえ、偏見については交流級での担任の影響が大きいです。
支援級の子でも、朝の会や学級活動などを普通級の子と一緒に受けることはないでしょうか?
その時の交流級の担任の態度は、大きな影響を与えます。
支援級の子だと、交流級の子と壁ができてしまいがちです。
しかし、担任が「〇〇さんも、一緒に入れてあげて〜」などと声掛けをするような人だと障がいに対する壁がなくなってきます。
こういった良いクラスに属している場合は、それほど偏見に悩まされることはないでしょう。
反対に、交流級の中で支援級の子を放置しているような担任もいます。
「自分は普通級の子だけ見てればOK。支援級の方は好きなようにやって」みたいなスタンスですね。
こういった悪い担任の態度は、子どもにも影響を与えます。
担任が支援級の子を放置していると、そのクラスの子も偏見を持つようになるのです。
なので偏見がどれくらいなのかは、自分がいるクラスによって大きく違ってくるかと思います。
保護者の偏見

次に、保護者同士の偏見ですね。
これも、多少はできてしまうものだと思います。偏見は避けられないことでしょう。
とはいえ私のクラスに在籍していた子の保護者は、普通級の保護者と仲良くしていました。
なので、それほど気にする必要はないかと思います。
大人ですし、ある程度障害に対する理解もあるでしょう。
また、保護者同士でガッツリ会うのって「授業参観」の時くらいだったりします。
それほど多くはないんですよね。そして、授業参観の時も皆さん自分の子供に夢中だったりします。
他の子を見たりはしていません。なので、それほど偏見を気にする必要はないかと思います。
それよりも、支援級の保護者同士の絆の強さに驚かされます。
支援級には毎朝、保護者が子供を送りに来ているケースが多くあります。
その時に保護者同士でたくさん話をしているんですよね。
これって、すごく貴重な時間だと思います。普通級では味わえないですよ。
支援級の保護者は絆を深めることができるので、偏見なども一緒に乗り越える仲間ができることだと思います。
すごくいいことだと思います。
もし偏見を受けたら
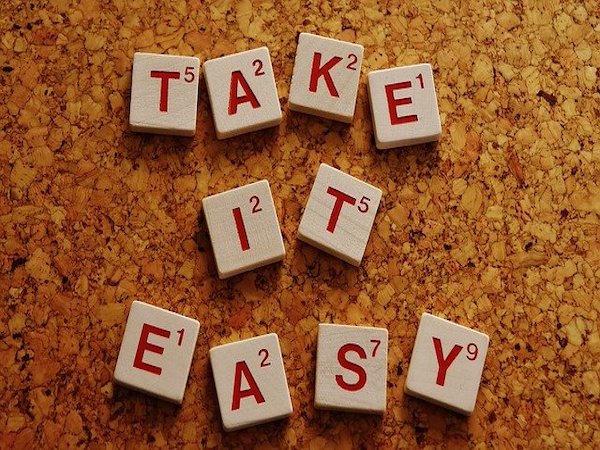
とはいえ、もしあまりにもひどい偏見を受けたらどうしようと不安に思っている方もいると思います。
きちんと解決をしておきたいですね。
結論から言うと、まずは「支援級の担任に相談」してみるのが良いと思います。
支援級の担任→学年主任→学校全体というように情報共有されていくはずです。
学校によっては、そういった子供の悩みを職員会議などで話し合ったりもしていますから良い状況になりやすいと考えて良いでしょう。
また、在籍している交流級で面談などを受ける機会があれば「交流級の先生に相談」するのもありでしょう。
偏見は、交流級の子から支援級の子に対してされますよね。
なので、交流級の先生に直接相談するのは効果的でしょう。
上記の2つでも変わらないようであれば、最終手段として「管理職に相談」するのが良いです。
とはいえ、担任に相談する前にいきなり管理職に相談するのはあまり良くないです。
担任の立場をなくしてしまうので・・・。
なので、最初は担任に相談するようにしましょう。
子供は親の影響を受ける

偏見について親が悩んでしまうことは多いと思います。
とはいえ、お子さんは親の影響をすごくたくさん受けます。
なので親がずっと悩んでいるようだと、子供もどんどん落ち込んでくることでしょう。(支援級に限ったことではないですが。)
なので大変だとは思いますが、「偏見なんて気にしない!」くらいの強い気持ちでいる方が子供にとってもプラスになると思います。
特に年齢が低い学生時代のうちは、周囲からの偏見を大きく受けやすいと思います。
周囲が大人になれば障がいに対する理解も深まるでしょうし、会社も障害者雇用率が決まっていますから障がいを持つ方に対する偏見はなくさなければいけません。
まずは親がハッタリでもいいので、強い気持ちでいられるとかなり良いかと感じます。
まとめ
偏見については、かなり悩んでしまうポイントだと思います。
今回の記事を参考にしつつ、場合によっては周囲に相談しながら解決していただけると幸いです。


