お子さんが障がいを持っているけれど、普通級に通わせたいと考えている保護者の方は多いと思います。
普通級の授業を受けたいと考えるものですよね。
- 障害児が普通学級に通うとどうなるのだろうか。
- 実際の現場目線で知りたい
上記のように考える人に向けて、元支援級担任の立場から記事を書いていきたいと思います。
3分程度で簡単に読むことができますので、ぜひ見てみてください。
障害児が普通学級に通うとどうなるか

障がいを持つお子さんが普通級に通った時ですが、軽度であればそれほど問題ないと思います。
1年生の時に支援級に入学した軽度のお子さんがいたのですが、特に大きな問題はなく2年生になった時に普通級に戻りました。
その後、普通級でも問題なく過ごしていました。
普通級でもいろんな子がいます。学力もそれぞれですし運動能力も異なっています。
そんなことから、軽度の障がいであればおそらく普通級でもなじめるはずです。
ただ障がいが重い場合は、無理して普通級に通わせるのはおすすめしません。
親としては、どうしてもお子さんを普通学級に通わせたいと考えることは多いと思います。
しかし、今の学校現場の多くは「叱る」ことが中心です。先生たちもかなりピリピリしている人が多くいます。
行動が遅かったり、友達関係が悪かったりすると障がいをもつ子は毎日のように怒られることが想像できます。
子供は自信を失うでしょうし、最悪の場合不登校になってしまうことも考えられます。
また普通級は子供の数が多いので、教員のサポートも少ないです。
友達もある程度は助けてくれますが、自分で考えて動くことが求められます。
なので、しっかりと自立して行動することが求められるでしょう。
もし普通級に入る場合は、障がいで困っていることなどをあまり担任の先生に伝えない方が良いかと思います。
担任も、障がいのあるお子さんという第一印象で接することになります。
そうすると、お子さん自身が嫌な思いをしてしまうでしょう。
障がいごとの解説

次に、障がいごとに普通級に入るとどうなるかを解説したいと思います。
実際に普通級に入れた時の様子なので、割と参考になるかと思います。
自閉症
自閉症のお子さんが普通級に入ると、マイペースで行動することが多くなると思います。
マイペースで動くこと自体は悪いことではなく、程度によるといったところです。
優しい友達がいるクラスだと、声かけをしてくれたりフォローしてくれるケースもあるでしょう。
そういった助けがあれば、問題なく行動できることが多いです。
あとは、朝の決まったルーティーンなどがある子もいますよね。
登校した後は、「必ず〇〇をする」といった決まりを持っている子もいます。
しかし、普通級では朝の時間にやることが毎日異なっていたりします。
「朝読書」「読み聞かせ」「合唱練習」「全校集会」など異なったことをするときに、自閉症の子がパニックにならないかは不安なところでしょう。
あと、普通級は水道やトイレなどの待ち時間があるのでしっかりと待つことができるのかというのも不安なところです。
普通級のクラスがかなりざわざわしているので、音でパニックにならないかも意識しておくべきことでしょう。
上記の点で、特に問題がないようであれば普通級で過ごすことが可能だと考えています。
ADHD
次に、ADHDのお子さんについてです。
ADHDではないか・・・?と思うようなお子さんも普通級にはいるので、割と普通級になじみやすいのではないかと思います。
中学年までは支援級にいたものの、高学年から普通級に移って過ごしている子も見ています。
割と問題なく過ごせるのではないかと思います。
ADHDのお子さんは、いろんなことに注意が向くのが特徴だったりします。
特別支援では周囲を囲って刺激を少なくしたり、イスの下にテニスボールをつけるなどして音を少なくする工夫があります。
また、支援級自体が人数も少ないので落ち着いて過ごしやすいといえるでしょう。
しかし、普通級になると状況が一気に変わります。
友達の数も多いですし、掲示物も多い。音もたくさんするでしょう。こういった環境にADHDの子が馴染めるのかを考える必要があります。
パニックになって、友達とトラブルを起こさないかどうかも意識すべきですね。
またADHDの子はただのヤンチャな子として見られることがあるので、学校内でも特に厳しい先生が担任になることが多いと思います。
萎縮してしまったり、怖がってしまって学校生活が嫌にならないかなどを検討する必要があるでしょう。
ダウン症
ダウン症のお子さんについては、私は普通級に在籍をしているのを見たことがないです。
普通級に通うのは、かなりハードルの高いことだと考えても良いでしょう。
ですが学校によってはインクルーシブ教育なども進んでいると思います。ダウン症の子も一緒に学べるケースがあるかもしれません。
ダウン症のお子さんにありがちなのが、着替えや準備などに多くの時間がかかってしまうことです。
普通級では毎日の授業がスピーディーに変わっていくので、これに対応していくのが難しいことがあるかもしれません。
また、頑固さもかなりあったりしますね。
お子さんにもよりますが、支援級でも自分が使いたいおもちゃを手放さずに友だちとトラブルになってしまうことなどがあります。
普通級だと本や教材など友達と一緒に使うものが多くあります。
友達とスムーズに貸し借りができるかどうかも重要なところでしょう。
学校や担任の様子で決める
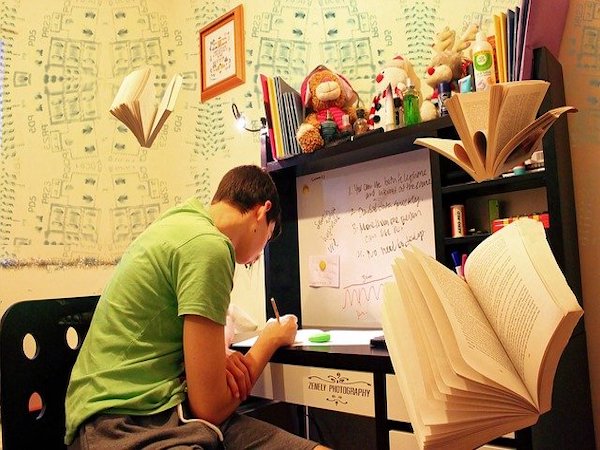
障害児が普通級でうまくいくかどうかは、学校や担任の状況によって決まることが多いです。
学校によっては、少しでもグレーの子がいたらすぐに支援級に送るようなケースもあります。反対に、明らかに障がいがあるにもかかわらず普通級で一緒に学んでいることもあります。
このあたりの基準が、学校によってバラバラなのが現状です。
なので障がいをもっていても、普通級で学べそうな雰囲気なら最初は普通学級に行かせてみるのがおすすめです。
以下の記事でも、詳しく解説しています。
また、どうしても子どもが学校の雰囲気に合わなそうであれば「引っ越し」するのもありだと思います。
引っ越しは家庭の事情にもよるので、簡単なことではないかもしれません。
しかしインクルーシブ教育を積極的に行なっている学校もありますので、そういった学校に行くことで子供が過ごしやすくなるかもしれません。
引っ越しのメリットは大きいと思っています。
まとめ
障害児が支援級に行くということですが、障がいの程度によって状況は変わってくると考えて良いでしょう。
今回の記事を参考にしつつ、検討していただければ幸いです。



