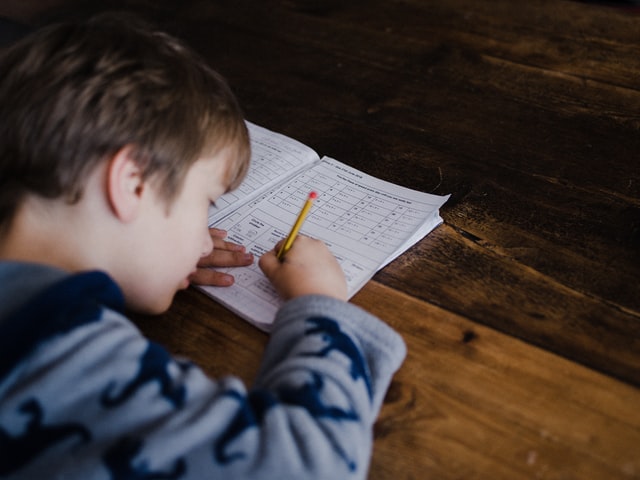発達障害の子の中にも、勉強ができるケースがあったりすると思います。
勉強ができる子と苦手な子がいたりするので、違いがよくわからなかったりしますね。
- 発達障害で勉強ができる子はどんな特徴がある?
- 専門家の目線で詳しく知りたい。
上記のように考える人に向けて、元支援級担任の立場から記事を書いていきたいと思います。
2分程度で簡単に読むことができますので、ぜひ見てみてください。
発達障害で勉強できる子の特徴について

発達障害で勉強ができる子についてですが、大まかに以下のような特徴があります。
3つほどあげましたので、ぜひ参考にしてみてください。
情緒障がいである
1つ目は、情緒障害のケースです。学力が低かったり、クラスの授業についていけない場合は「知的障がい」であることが多いです。
しかし情緒障がいだと、学力的には特に問題がなく普通に取り組めていることが多いですね。ADHDや自閉症などの障害だと勉強ができるケースが多かったりします。
ただ、情緒障がいについては勉強をさせるまでが結構大変だったりします。友達とトラブルが起こっては勉強が手につかないでしょう。
自閉症でも、ルーティーンを崩してしまうとパニックになってしまうことがあります。
なので、勉強よりも取り組ませるまでの過程の方が大切になるといえるでしょう。
配慮がされている
勉強がしやすいように、しっかりと環境が配慮されていることも大切です。
障がいを持つ子は感覚が過敏だったりするので、環境によって勉強ができたりできなかったりするものです。
まずは、しっかりと集中できる環境を配慮していくようにしましょう。できるだけ刺激を少なくすることが大切です。
散らかっている部屋だったりすると、余計なものがたくさん目に入って大変ですよね。ADHDのお子さんだったりすると集中しにくくなるでしょう。
また、音の刺激を減らして集中できる環境を作っていくことも必要です。支援の方法として、椅子の裏にテニスボールを付けたりして音を減らしているケースもあります。
障がい特性に合わせて、細かい配慮をしていくことで子供がより学習に取り組みやすくなってくるのです。
周囲に良い大人がいる
良い大人が周りにいる場合は、発達障がいであれ勉強に取り組めるケースは多いです。
健常児でも、周囲の大人の影響はとても大きかったりするものです。
大切なポイントとしては、障がいを1つの個性として受け止めてくれることです。障がいを悪いものだと捉えてしまうと子どもは自信をなくしてしまいます。
勉強が嫌になりますし、どんどんやらなくなってしまうでしょう。
そうではなくて、1つの個性としてありのままに認めてあげることが大切です。
たとえば、電車に対して興味が強いのであればたくさん誉めることも大切です。
電車についてもっと自分で勉強しようと思いますし、それがきっかけで勉強自体にも興味が持てるようになるでしょう。
しっかりと子どもに寄り添いながら支援をしていくことは欠かせないことです。
興味を持っている子が多い

発達障害の子は特定のものに興味を持っていることが多いです。
「ゲーム」かもしれませんし、「動物」かもしれません。しかし、その興味を大人がしっかりと認めることで勉強ができるようになってきます。
なぜなら、何かに興味をもつということは勉強ととてもよく似ているからです。
例えば、ゲームに興味を持てばキャラクターを調べたり強い勝ちパターンを覚えたりすると思います。この調べる過程は、勉強をするのとよく似ています。
だんだんと、スムーズに勉強ができるようになってくるでしょう。
子供が、学校の勉強と関係ないことに取り組んでいたら嫌な気持ちがするかもしれません。
しかし、まずは学習の習慣をしっかりと作ってあげることが勉強ができるようになるための近道だったりします。
まとめ
勉強ができる子の特徴などを挙げてきました。
今回の記事を参考にしつつ、実践してみてください。